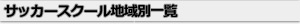日本代表・吉田麻也選手が過ごした少年時代 フォワードからディフェンスへの転身
2015年01月16日
メンタル/教育現代の日本人選手のなかでフィジカルの強さと足元の技術を持つセンターバックは貴重な存在です。そのどちらも高水準で兼ね備える吉田麻也選手の存在は今の日本代表のなかで欠かせない選手の一人にです。そこで今回は吉田麻也の原点を振り返ります。
文●元川悦子 写真●Getty Images
※『僕らがサッカーボーイズだった頃 プロサッカー選手のジュニア時代』より一部転載
世界でも通用する人間に
江戸時代には日蘭貿易の玄関口にとなり、グラバー園や大浦天主堂などが外国に由来する観光施設が立ち並ぶ長崎市。異国情緒あふれるこの町で、88年8月に生を受けたのが、吉田麻也である。
吉田有(あり)、昭子夫妻にはすでに長男・穂波、次男・未礼という年子の男の子がいたが、三男・麻也は長男より7つも下。歳が離れた末っ子の誕生を家族みんなが喜んだ。
麻也という名前は、父・有さんの姉夫婦が名づけた。
「私たち夫婦が共稼ぎだったこともあり、子どもたちは近所に住んでいた夫の姉夫婦に預けていました。麻也の名前も姉夫婦がつけてくれて、『世界でも通用する名前をつけたい』という希望で、呼びやすい『マヤ』にしたと聞いています。こうやって世界で活躍するようになってくれて、うれしい限りです」(昭子さん)
両親が忙しかったことから、麻也少年はいろんな人の手で育てられた。毎日のように面倒を見てくれた叔父叔母の家では「赤ちゃんにベビーフードを食べさせてたらダメ。特にカルシウムをたくさん取らないといけない」という考えがあり、魚のすり身やいりこをすったものをよく食べさせてもらっていた。
両親がそれほど大きくないのに、彼が189センチもの長身になったのは、こうした食事の影響かもしれない。

家の前の坂道でボールコントロールに磨きをかける
そんな彼が、当時から小学校時代にかけて特に頻繁に取り組んでいたのが、家の前の坂道でのボールコントロール練習だ。
「坂道だと、ボールを蹴ったら跳ね返ってくるじゃないですか。小さい子だと、そんなに飛ばないから、ちょうどいい感じで跳ね返ってくる。そういうコントロール練習をよくやってました」と本人も懐かしそうに話す。
長男・穂波さんも弟のボール扱いの練習によく付き合った。兄はボールを転がす側に入るのだが、スピードや勢いを変化させれば、幼い弟はそれに合わせて動かないといけない。
GKだった7歳年上の兄は、しっかりと顔を上げて視野を確保しながら正確に止めて蹴ることの重要性をよく理解していたから、小さな弟にもそれを叩き込もうとした。
「麻也は結構左足でも蹴れますし、視野も広い。今考えると、あの坂道の練習はすごくプラスになってるのかなと思いますね」
今は少年サッカー指導に携わっている穂波さんが冷静に分析する。
麻也少年は小さい頃から体が大きく、同年代の仲間たちとボールを蹴るときは、高さと強さだけで勝てる傾向が強かった。が、兄たちの中に入るとただのちびっ子になってしまう。「自分は全然、下手なんだ」と思わせ、一生懸命スキルを身につけようという意欲を高めてくれる年長者が身近にいたことは、彼のレベルアップにつながった
佐古小学校の少年団(のちに南陵FCに改名)に入って、本格的にサッカーを始めたのは小学1年生のとき。麻也少年は仁田(にた)小学校に通っていたのだが、その少年団は3年生からしか入れず、隣の佐古(さこ)小学校は1年生から入れる。そういった経緯もあり、彼は佐古小の少年団を選んだ。
といっても、長崎市内の場合、目と鼻の先にふたつの小学校が隣接しているケースが結構ある。仁田小と佐古小がまさにそうで、両校は歩いて2~3分の距離。吉田家から通うのに支障は全くなかった。
ただ、問題は帰り道の急坂だ。「行きは自転車で2~3分で着いてしまうけど、帰りは歩いて10分以上かかる」と穂波さんは話していたが、この登り坂で、足腰は相当鍛えられた。しかも南陵の指導者が厳しかったため、子どもの頃から苦しさを学ぶことができた。
FWだった少年時代
サッカー熱が高じた麻也少年は、平日週3回の南陵の練習に加え、仁田小の少年団の練習にも顔を出していた。学校の仲間とも仲が良く、和気あいあいとしていたが、試合になると別。両者が対戦するときは周りを巻き込んで物々しいムードに包まれた。
南陵の方が老舗クラブで保護者たちのプライドは高い。一方の仁田小を応援する人たちのライバル意識も少なからずある。吉田は「クラシコ」と称したが、それだけ熾烈なバトルが繰り広げられたのだ。
「麻也が5年生の時に両チームの死闘がありました。長崎の別の小学校の保護者までが見に来て、すごい熱気だったのをよく覚えています。試合は仁田が早い段階で2点を入れて、南陵が1点を返したあと、仁田がさらに2点を加え、4対1になった。
私たち親も『もうだめだ』と思っていました。ところが、試合終盤に南陵が3点を入れて同点に追いついたんです。結局、PK戦になり、どっちもエースが外したんですが、最終的に南陵が勝ちました。麻也はFWだったんですが、相手にピッタリつかれて結構激しく削られていたので、私たち親も心配になったほどです」
昭子さんは忘れられない名勝負を今一度、振り返ってくれた。
母がハラハラドキドキしながら息子のプレーに注目する傍らで、父はじっと黙ってビデオを撮影していた。有さんは中学・高校でサッカーをやっていたが、「子どもの指導はコーチに任せるべき。親は一切、口を出すな」という哲学をもっていて、自ら子どもたちを叱咤激励することはしなかった。
「父親はビデオを撮ってるイメージしかない」と吉田も言う。ただ、その映像が彼の成長の助けになったのだから、父もうれしいだろう。
「家に帰ってそのビデオをみんなで見て、兄ちゃんがちょいちょい何か言ってくるというのはよくありましたね。それが習慣になって、自分が出た試合の映像は毎回、見るようになりました。今では当たり前になっていることだけど、その頃が始まりですね」
今や日本代表の軸となった吉田は、自分のプレーやチーム全体を客観視できるところがひとつの長所だが、それも幼い頃からの積み重ねだった。
人生を大きく変えた兄からの手紙
今や日本代表の軸となった吉田は、自分のプレーやチーム全体を客観視できるところがひとつの長所だが、それも幼い頃からの積み重ねだった。
小学5~6年生になると、麻也少年は大型ストライカーとして地元ではそこそこ知られる存在になっていた。GKだった穂波さんを相手にシュート練習やヘディング練習を重ねた効果もあり、長崎市内の試合ではかなり活躍していた。
長崎市トレセンにも選ばれたが、父・有さんが「麻也が抜けると南陵のチームが困るだろう」と言っていたことから、あまり練習には参加しなかったという。
このため、選抜チームでの遠征や、全日本少年サッカー大会といった大舞台はほとんど経験していない。本人も「サッカーは一生懸命やっていたけど、まあまあ好きくらいだったかな。他のことも楽しみたい気持ちが強かったですね」というくらい、軽く考えていた。
「プロサッカー選手になりたい」と真剣に考えたこともなければ、家族にそう打ち明けたこともなかった。
「親の私が見ていても、『もうちょっと頑張ったらいいのに……』と思うことは、結構ありました。そこそこ努力はするけど、何が何でも自分を追い込むような子ではなかったですから。
サッカー以外にもバスケットやローラースケート、ギターやピアノとやりたいことがいっぱいあったようですし、私たちも忙しかったので、好きなことをしてくれればいいと思っていました。
まさかプロ選手になるなんて、夢にも思いませんでしたね」と昭子さんは語る。
そんな麻也少年の人生を激変させるきっかけを作ったのは、長男・穂波さんだった。
彼が小学6年生になった春、博多で浪人生活を送っていた穂波さんは、インターネットカフェで大学検索を終えたあと、Jリーグ下部組織のセレクション情報をふと目にした。ジュニアユースのセレクションがあるのは名古屋U-15とガンバ大阪ジュニアユースだけ。
「名古屋なら親戚がいるな」と思った兄は、店のスタッフに言ってこのページをプリントアウトしてもらい、「吉田麻也様」と宛名を書いた郵便を実家宛てに送った。長男から届いた紙を見た母は、末っ子に『どうする?』と尋ねた。
観光気分で行ったセレクション
本人は「まあ、行ってみるか」と、興味本位で答えた。多忙な母が長崎から名古屋へ息子を連れていくのは、通常ならかなり難しかった。麻也少年がラッキーだったのは、昭子さんの姪っ子が生まれたばかりだったこと。
会いに行こうと思っていた日が名古屋U-15のセレクションと全く同じタイミングだったため、「じゃあ、ついでに行こうか」と息子に声をかけることができたのだ。本人も最初は旅行気分だった。
「僕自身、観光のノリでした。名古屋へ行くのも2回目くらいだし、どうせムリだろうと思ってたから。Jリーグの下部組織っていうのは、全国から有名な選手が受けに来て、受かるのは1、2人だと考えていました。
でも実際は名古屋に通える範囲の子しか来ないから、東海地域の選手ばかりなんですよね。試験官だったルーマニア人のアイザック・ドールに『え、長崎から来たの?』って言われたくらいです」
1回目のゲームでは中盤でプレーして何とか突破。最終テストとなる2回目を迎えた。そこで、麻也少年の人の好さが出てしまう。
坂道練習などを通じて左足のキックに磨きをかけてきた自信があったせいか、チームわけのときに「左サイドバックでもいいよ」と言ってしまったのだ。
その通り、左サイドバックのポジションを託されたが、普段からやっていない位置で自分らしさを出せるはずがない。クロスどころか、ボールさえ満足に触れなかった。
タイムアップの笛が鳴った瞬間、「完全に落ちたな」と思った。この様子を遠くから見ていた昭子さんにも、息子の落胆ぶりが手にとるようにわかった。
この直後、麻也少年ら5~6人はアイザック・ドールに集められ、何かの紙を受け取った。母は参加者への労いが書かれた手紙だろうと考えていた。
だが、歩いてきた息子からは驚くべき言葉が発せられた。
「受かったし」
子どもたちの希望を優先する両親の方針
保護者にも説明があるということで、母・昭子さんはビックリして行ってみると、「来年から名古屋に来られますか?」といきなり聞かれた。寮があるのかと思っていたが、名古屋の場合、ジュニアユース年代までは家族と同居して通わなければならなかった。
そこで、まずは姪が暮らす名古屋の家に下宿させればいいと考え、「大丈夫です」と返答した。
長崎に戻ると、サッカー好きの父・有さんは喜んでくれた。博多に住む穂波さんも、麻也少年の将来を考えたらプラスだと確信していた。
「長崎には国見高校とか全国レベルのチームはあるけど、やっぱりJリーグのクラブがないし、情報が届くのが遅い。プロというものに対して現実味がない。でも名古屋に行けばそれが夢の世界じゃなくなる。僕はすごくいいと思いましたね」(穂波さん)
とはいえ、かわいい末っ子が小学校を出てすぐに親元を離れて暮らすというのは、普通の親なら抵抗があるのではないか。
しかも麻也少年が小学校を卒業するのと同時に、次男・未礼さんも東京の専門学校に進むことになった。
家族がバラバラになれば経済的負担も増す。それでも吉田家の両親は 「子どもたちにできることは全部やってやりたかった」とそれぞれの希望を優先した。
名古屋U-15の練習は週1回の休み以外はほぼ毎日あった。1年生のときは井森秀歩コーチ、2~3年生は今久保隆博コーチから指導を細かく受けた。
特に井森コーチの頃は基礎が多かった。リフティング500回など基本中の基本を叩き込まれたが、小学生時代はキックやシュートをメインにやりながら楽しくプレーしていた吉田はうまくできない。
100回できれば御の字だった。長崎を離れる前、友達と遊びまくって練習を怠ったツケも回ってきて、体力不足も明らかだった。新天地での練習に慣れるのはかなり大変だった。
「グランパスに入って最初の頃、『20人中、何番くらい?』と聞いてみたことがありました。麻也は『下から3番目かな』と言う。『それで大丈夫なのか?』と自分が問いかけると、本人も何やら考え込んでました。
すると、直後くらいから朝早く起きてランニングをしたり、練習後に入念にストレッチをやったりするようになったんです。本人も危機感を覚えたんでしょうね」(穂波さん)
親元を離れ、プロ選手になることを決意
引っ越しから2~3カ月が経過し、ボランチとして試合に出るようになった吉田は、まずまずのプレーをして井森コーチに褒められた。
小学校までFWだった彼がボランチで使われたのは初めて。だからこそ、うれしさもひとしおだった。その気持ちを素直にサッカーノートに書いて提出したところ、コーチからは予想以上に厳しい言葉が返ってきた。
「ちょっと褒めたくらいで、満足しちゃだめだ」と。
このことを、吉田は今もよく覚えている。
「新たな環境に行って、自分の力を知らしめたいと強く思っていたんですよね。その機会がなかなか来なくて、やっとアピールできた。ひと安心したのはありました。でも慢心したらダメなんだと井森コーチの一言で気づかされた。そこからは常に課題を探すようになったし、90分満足したことは一度もないですね。サッカーにパーフェクトってのはありえないですから」
吉田は向上心を持ちつづける大切さを心に刻んだ。

プロフィール
元川悦子
(もとかわ・えつこ)
1967年、長野県生まれ。業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーランスのサッカージャーナリストとして活躍中。現場での精緻な取材に定評があり、Jリーグからユース年代、日本代表、海外サッカーまで幅広く取材。著書に『古沼貞雄・情熱』(学習研究社)、『U-22』(小学館)、『黄金世代』(スキージャーナル)、『いじらない育て方 親とコーチが語る遠藤保仁』(NHK出版)、『高校サッカー監督術 育てる・動かす・勝利する 』(小社刊)などがある。
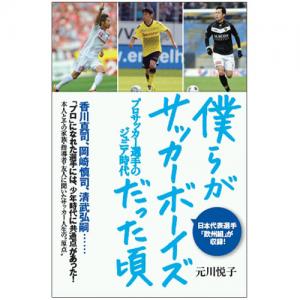
『僕らがサッカーボーイズだった頃 プロサッカー選手のジュニア時代』
【商品名】僕らがサッカーボーイズだった頃 プロサッカー選手のジュニア時代
【著者】元川悦子
【発行】株式会社カンゼン
四六判/256ページ
2012年7月23日発売
香川真司、岡崎慎司、清武弘嗣……
『プロ』になれた選手には、少年時代に共通点があった!
本人と、その家族・指導者・友人に聞いたサッカー人生の“原点”。
プロの道を切り拓いた背景には、「家族」の温かい支えと、転機となる「恩師」「仲間」との出会いがあった。
『ジュニアサッカーを応援しよう!』の人気企画が待望の単行本化!!
※ご購入はカンゼンWEBショップまで
カテゴリ別新着記事
ニュース
-
 【AFC U17女子アジアカップ インドネシア2024】U-17日本女子代表メンバー発表!2024.04.15
【AFC U17女子アジアカップ インドネシア2024】U-17日本女子代表メンバー発表!2024.04.15
-
 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!2024.04.11
「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!2024.04.11
-
 「東北トレセンU-13」が開催!2024.04.10
「東北トレセンU-13」が開催!2024.04.10
-
 【AFC U23アジアカップ カタール2024】U-23日本代表メンバー発表!2024.04.08
【AFC U23アジアカップ カタール2024】U-23日本代表メンバー発表!2024.04.08
フットボール最新ニュース
-
 近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.17
近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.17
-
 「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.17
「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.17
-
 【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.17
【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.17
-
 リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.17
リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.17
-
 前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.17
前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.17
大会情報
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
お知らせ
ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |
人気記事ランキング
- 【AFC U17女子アジアカップ インドネシア2024】U-17日本女子代表メンバー発表!
- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【西日本】
- かつて“怪物”と呼ばれた少年。耳を傾けたい先人の言葉
- 興味と探求心を育む松井大輔の指導「個人戦術を身につけることができれば…」横浜FCスクール初指導で子どもたちに伝えたこと
- ジュニア年代にも大切なトップ選手の共通点は?“自重コントロール”の重要性【フィジカルのプレーモデル】
- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例
- 自分よりも大きくて速い選手も1対1で抑える。内田篤人から学びたい守備時の姿勢【フィジカルのプレーモデル】
- 「2023ナショナルトレセンU-14 (後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- 栄養も食事量も“バランス良く”/小学校1・2年生向けの一日の食事例
- 「2023ナショナルトレセンU-13 関東」参加メンバー発表!