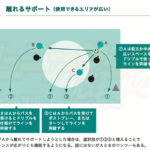起こってからでは遅い『スポーツ事故』の問題。指導者・保護者が心得ておくべきこと
2017年06月30日
インタビュー2004年、愛媛県今治市内で次のような事故が起こりました。小6男児(当時)が小学校のグラウンドでFKの練習をしていた際、そのボールがゴール後方の塀を越え、オートバイを運転していた高齢者がボールを避けようとして転倒。事故から約1年半後に死亡したという事故です。遺族側は男児の両親を相手に訴えを起こし、二審では、両親に対して約1180万円の損害賠償が命じられました。しかし、2015年4月、最高裁では二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けたのです。この最高裁での判決は大きな反響を呼び、子どものスポーツにおける安全性という観点から、波紋を投げかけました。本稿では2回に渡って、スポーツ事故に詳しい望月浩一郎弁護士にお話を伺い、学校を含めたスポーツ施設の現状や問題点、保護者や指導者が心得ておくべきことを指南していただきました。
(取材・文●三谷悠 写真●ジュニサカ編集部)

問われるのは場所を提供する側の管理責任
まずは望月弁護士に、2004年に愛媛で起きた事故についての見解を聞いた。
「スポーツ施設で使用しているボールが、ふとした拍子に外に出て、事故が起こるなどのケースはサッカーに限らず多々あります。たとえば野球場において、打者の場外ホームランのボールが駐車場まで飛んでいき、車のフロントガラスが割れたとします。この場合、ホームランを打った選手に責任は生じるのでしょうか?
答えはNOです。
そのスポーツのために提供されている施設の場合、利用する側は、施設がそのスポーツを行うのに適していると考えています。そのため、上記の野球の例でいえば、「ホームランは打ってもよいが、場外ホームランは打ってはダメ」ということにはなりません。
ホームランは野球でいえばよいプレーであり、決して悪意のあるものではないので、責任を負う必要はないのです。場外ホームランを打って他者に損害を与えるならば、その原因は、施設が野球を行うにふさわしい施設でないことになります。
その場合は、この施設は野球を行うにあたり「通常有すべき安全性」に欠ける施設として、場外ホームランで被害を受けた人の損害を賠償する責任が生じます(民法727条、国家賠償法第2条) 。
サッカーをすることが予定されている施設、また野球場、ゴルフ場など、それぞれの競技をすることが予定されていた施設では、その競技をおこなうことで第三者に危害が加わることを防ぐ施設であることが求められます。プレーヤーは、その施設を本来の目的通りに使用している限りは、基本的に責任は問われないという考え方です。
今までも、同様のケースはありました。九州のある市立小学校で、グランドでサッカーの練習をしていた11歳の男子が蹴ったサッカーボールが職員室に飛び込み、職員が受傷しました。この事故では、サッカー練習中のボールが職員室に入るような校舎・運動場の構造や管理に問題があるとして市の責任が認められています。
愛媛の事件の場合、そもそも原告側がこういう訴えを起こすこと自体に賛成できません。裁判の機能は直接的には被害の補償ですが、事故の原因を明らかにし、再発防止につなげるという機能もあります。この後者の目的からは、再発を防止するためにはどこに責任があるのかを考えて被告を選定してほしいと思います。
ボールを外に出そうと意図的に蹴った場合なら話は別ですが、技術的に未熟だったために起こったとしても、そのことが悪いということにはなりません。私としては最高裁で、それまでの判決が是正されてよかったと思っています」

両親の監督義務が争点になったとされるが、最高裁は「親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ない」という見解を示した。保護者の監督義務とはどこまで問われるものなのだろうか。
「法は、責任能力のない年齢の者(判例上は小学校5~6年生程度が限界とされています)には損害賠償の責任を認めていません。一方で、責任無能力者の行為で損害を受けた者を保護する必要がありますから、責任無能力者の加害行為については、「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」(子どもの場合には両親)に責任を負わせています。
この法定監督者の責任が免除される場合があり、法は、「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」(民法714条第1項)と定めています。
一審、二審は、両親には、子どもが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務があると判断しました。これに対して、最高裁判決は、監督義務は“一般的なもの”であり、具体的には、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、その行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められる場合に限り、子に対する監督義務違反が認められるとしています。
この事件では、本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしても、ボールが本件道路上に出ることが常態であったものではなく、具体的に(事故の発生が)予見可能であるとの特別の事情は認められないと判断しています。この点が結論を分けています。
子どもがサッカーゴールとサッカーボールを本来の目的で使用しているにもかかわらず、ボールが校外に飛び出たことで生じた事故は、子どもやその両親の責任ではなく、学校施設の安全性ないし管理者の責任が問題とされるべきです。
カテゴリ別新着記事
ニュース
-
 U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
-
 U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
フットボール最新ニュース
-
 近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
-
 「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
-
 【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
-
 リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
-
 前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
大会情報
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
お知らせ
ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |
人気記事ランキング
- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!
- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!
- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは
- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」
- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素
- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例
- 一生懸命走っているように見えない息子
- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」
- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること