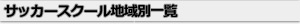「日本らしいサッカー」とは何か。メソッドの源流を辿る
2020年06月04日
戦術/スキル昨年出版された元日本代表監督・岡田武史氏の著書「岡田メソッド」が話題を集めたように、日本サッカー界には様々なメソッドが存在している。1990年代に渡来した「クーバーコーチング」のような欧州から輸入されたメソッドもあれば、独自に発達したメソッドも存在しているように、複数のメソッドが乱立しているのが現状だ。岡田メソッドはスペインの強豪FCバルセロナのメソッドを参考にしているように、欧州のメソッドを日本サッカーの文脈から再解釈するパターンもある。今回は、6月8日発売となる『フットボール批評 issue28 』の企画『メソッドの源流を辿る』から一部抜粋して紹介する。
『フットボール批評 issue28』 より一部転載
文●結城康平 写真●Getty Images

そもそも『メソッド』とは何なのか?
先ず、メソッド(Method)という単語についての論考が必要となる。
何故なら、日本におけるメソッドという単語は、ゲームモデルからトレーニング手法までの広域をカバーしているからだ。例えば「岡田メソッド」では、下記のインタビューが参考になる。
「やっぱりさっき言った共通認識を持たせるようなこと、どういうサッカーをやるんだっていうプレーモデルをまず作って。そのプレーモデルを理屈よりもトレーニングでどうやって落としこむかっていうトレーニングを『岡田メソッド』って呼んでて、プレーモデルをしっかり作らないといけないんだけど、プレーモデルっていうのはある程度僕らのイメージの中でできてきてるし、それをどういうメソッドで落としていくかっていうのは、今いくつかもう出てるんだけど。そういうものをしっかり作って、そこから育成までを全部指導者に徹底していかなきゃいけないから」(FC今治 公式サイトより)
岡田監督はトレーニング手法を「メソッド」と名付けているが、それにはスペインにおけるプレーモデルという概念が色濃く反映されている。他方、ドリブルやシュートに着目した技術指導的なスクールは独立した「トレーニング手法」に近い。
プレーの一部を塾として学ぶスクールは世界中にも点在しているが、特に日本やアメリカでは文化的な影響もあるのか特定の技術を磨こうという意識が強い。今治のアプローチはクラブとしての取り組みであり、ここに質的な差異は存在する。本来のメソッドという単語は恐らく教育学からの転用だと思われるが、メソッドという言葉に囚われる危険性については最初に述べておく方が賢明だろう。
トレーニング手法だけでなく、ゲームモデルやクラブの哲学を含んだ言葉としてUEFAの研究グループは「Playingstyle(プレーイングスタイル)」という言葉を使用することを推奨している。彼らによれば、プレーイングスタイルは国・クラブの育成を理解するのに有用であり、3つの要素を含んでいる。それが「identity (哲学)」「Principle(原則)」「System(システム)」だ。スペインを例とすると、「哲学」は「美しくボールを繋ぐ」ことであり、「原則」は「ポゼッションの重視」、「システム」は「4‐3‐3/4‐2-3‐1」となる。
このように考えていくと、岡田メソッドの本質は「クラブチームにおける統合的なプレーイングスタイルの構築」であると考えるべきだろう。単なるトレーニングメソッドの制作であれば珍しくないが、プレーイングスタイルの明確化を可能にする膨大な資料を作成・共有したクラブは少ないはずだ。
個人スキルをベースにしたトレーニングの源流
個人スキルをベースとしたトレーニングとして言及されることが多いのはドリブルだが、ストライカーの技術を習得することを目的とするスクールや守備のスクールも存在する。また、GKはポジションの特性上どうしてもチームのトレー
ニングから切り離されることが多く、セービングやスローイングなど個人技術のトレーニングが多い。そういった意味では、GKこそが最も「型」のトレーニングを重要視する傾向があると考えても良いはずだ。
実際に、個人の技術トレーニングは各国でも続けられている。例えばフランスのクラブでは、ユース世代の指導にドリルトレーニングが存在する。彼らは週3回、それぞれ30分間で個人スキルの向上を評価されており、様々なドリルトレーニングに正確に対応することが求められる。若くしてテクニック面に優れるフランスのアタッカーは、このような継続的な技術トレーニングによって育まれていると考えられている。
オランダはどちらかというとゲーム形式のトレーニングを重視しており、文脈に沿った技術トレーニングこそが有意義だと考える文化が残っている。しかし、アヤックスが徐々に個人スキルのトレーニングに時間を割くようになってきているように、徐々に変化が生じていることにも触れておく必要があるだろう。
スペインでもオランダと同様にゲーム形式のトレーニングが好まれるが、通常のトレーニング後に「テクニフィケーション・セッション」と呼ばれる補完型の個人技術トレーニングが追加されることが多い。特に技術面での向上が必要なポイントに絞り、指導者と共に弱点を克服していく。
イタリアでは歴史的にプレッシャーや相手の存在しないドリルトレーニングが多く使われているが、2010年のW杯を機に大胆に方針を変更。ゲームベースのトレーニングを増加させる取り組みを目指したが、現場では改革が進み切れていない部分もあるようだ。
特に戦術王国イタリアでは守備の細かなポジションを重要視することから、相手がいない状態で位置を調整するようなトレーニングが昔から多く、守備ではマークに特化したトレーニング、攻撃ではシュートに特化したトレーニングを好む。そのようなアプローチはスペシャリストを生み出すことに寄与してきたが、逆にゲームの中で柔軟にプレーすることが求められる近年、イタリアが苦しんでいる理由にもなっている。
つづきは発売中の最新号『フットボール批評 issue28』からご覧ください。
【商品名】フットボール批評 issue28
【発行】株式会社カンゼン
2020年6月8日発売
とある劇作家はテレビのインタビューで 「演劇は観客がいて初めて成り立つ芸術。スポーツイベントのように無観客で成り立つわけではない」と言った。
この発言が演劇とスポーツの分断を生み、SNS上でも演劇VSスポーツの醜い争いが始まった。 が、この発言の意図を冷静に分析すれば、「スポーツはフレキシビリティが高い」と敬っているようにも聞こえる。
例えばヴィッセル神戸はいち早くホームゲームでのチャントなど一切の応援を禁止し、 Jリーグ開幕戦のノエビアスタジアム神戸では手拍子だけが鳴り響いた。 歌声、鳴り物がなくても興行として成立していたことは言うまでもない。
もちろん、これが無観客となれば手拍子すら起こらず、終始“サイレントフットボール”が展開されることになるのだが……。
しかし、それでもスタジアムが我々の劇場であることには何ら変わりはない。 河川敷の土のグラウンドで繰り広げられる名もなき試合も“誰かの劇場”として成立するのがスポーツ、フットボールの普遍性である。 我々は無観客劇場に足を踏み入れる覚悟はできている。
カテゴリ別新着記事
ニュース
-
 U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
-
 U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
フットボール最新ニュース
-
 近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
-
 「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
-
 【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
-
 リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
-
 前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
大会情報
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
お知らせ
ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |
人気記事ランキング
- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!
- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!
- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは
- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」
- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素
- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例
- 一生懸命走っているように見えない息子
- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」
- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること