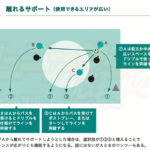「声が出ない大きな理由」は頭の中にある! 自然と声が出る環境づくりはできているか?
2020年08月05日
育成/環境「もっと声出そう!」といった漠然とした声かけをしている選手や指導者を見たことはありませんか。試合中や練習中において自分の考えやチームメイトへの指示など声かけが必要な場面は多々あります。つまり、声をかけて自分の意思を伝えることこそが声を出す目的なのです。ただ具体性のない声がけをしても意味はありません。しかし、そもそも何をどう声をかければいいのか頭の中で理解できていなければ自然と声を出すこともできません。では、どうすれば子どもたちは自然と声を出すことができるのでしょうか。本日発売となる『枝D ボールも自由も奪い取る術~守備からみるフットボールの新しい景色』より、“声が出ない大きな理由”について一部抜粋して紹介します。
『枝D ボールも自由も奪い取る術~守備からみるフットボールの新しい景色』より一部転載
文●内田淳二 写真●Noriko Nagano
【前回】ボールホルダーのほとんどは“利き足側への突破”を狙っている! 対人守備の基本動作『中西』とは

声が出ない大きな理由
フットボールのトレーニングや試合中に「もっと声出そう!」のような具体性のない声がけをしてしまったことはありませんか?
人と人が集まり、チームとして同じビジョンを共有していくためには、グループ間での「会話」は重要な意味を持ちます。しかし、「声が出せない・自然と出てこない」チームに限って「もっと声出そう!」という声がけが多く飛び交っている印象を受けます。
でもなぜ「声が出ない」のか?
全国をまわり、みなさんと枝Dの【規準】を共有しながらトレーニングをしていく中で、皆さんから与えていただいた「気づき」によって分かったことがあります。選手たちから声が出ないことには、きちんとした理由(背景)があったのです。日々、違う毎日を過ごす中で、気持ちがノッている日もあれば沈んでいる日もありますから、そういった外的要因が大きいメンタルの部分に関しては今回は置いておきますね。
メンタル面以外で「声が出ない」大きな理由は2つ。
②頭の中で「理解しているけど言語化ができない」状態。
の2つです。
当たり前のことのようですが、「声が出ない」理由のほとんどがコレです。
①は、残念ながら指導者が伝えていることやテーマとしている内容に選手の頭がついていっていない状態になります。トレーニングメニューの焦点が話している内容と違うことで余計に混乱していたり、「自然と」声が出てくるような設計が組み込まれていない状態です。
人は、頭で理解したことが成功体験につながっていく中で、次第にそれが「自信」に変わっていくものです。ですから、まず「頭が付いていっていない」のであれば、具体的な声なんて出せるはずがありません。もし、頭では分かっていたとしても、成功体験につながっていなければ(自分なりの攻略法を見つけていなければ)、自分のプレーに「自信」は持てません。「あっているのかな? 間違っているのかな?」と、そんな状態では大きな声を出せるわけがないのです。
さらに、今いる環境が「ミス」に敏感な環境であれば尚更。出来ないことを「ミス」と捉えてしまう環境では、声を出すことは至難の業でしょう。そもそも「ミス」なんてないんですけどね。出来ないことを出来るようにしていくために、日々練習をしているわけですから。変わろうとしないことは「ミス」と呼べるのかも知れませんが、それは選手たちや子どもたちだけに当てはまることではありません。
②は、指導者が伝えていることやテーマとしている内容に選手が置いていかれることなく付いてきているものの、選手自身が頭の中で分かっていることをどのように伝えたら良いのか「アウトプットができない」状態です。
選手の表現は一人ひとり違います。様々に飛び交う言葉の意味を、指導者側で勝手に汲み取って解釈してしまう環境だと、例外なく結果こうなっていきます。気持ちを汲み取ることは大切ですが、言葉が持つそのものの意味まで汲み取ってしまうと、喋る側の言語化力は育ちません。
お笑い怪獣と呼ばれている超大物芸人のMC術のように、ゲスト(選手たち)にどれだけ話題を振っておいしくする(喋らせる)かが重要なのです。裏では上手くまわしながらも、あくまでゲスト主体で全体を整えていくのがMC(指導者)の腕なのです。
「ミス」という概念がそもそも存在していない。間違いも笑顔で受け止めてくれる。表現しやすい環境である。大人が率先して失敗を見せたりする。大人も間違いを認めてくれる。小さなことでも自信をつけさせてもらえる。言葉の意味をそのまま純度100%で受け止めてくれる。話をちゃんと聞いてくれる。
そのような「安心」を感じられる環境を整えていけば、自然と「声は出る」ようになっていきます。個人個人の性格の話をするのは、その環境を整えてからにしましょう。
続きは『枝D ボールも自由も奪い取る術~守備からみるフットボールの新しい景色』からご覧ください。
【商品名】枝D ボールも自由も奪い取る術〜守備からみるフットボールの新しい景色〜
【発行】株式会社カンゼン
2020年8月5日発売
枝D(ディフェンス)とは、元Fリーガーである内田淳二氏が考案するまったく新しいディフェンス理論のことです。
サッカーやフットサルはもちろん、ゴールを目指す球技であれば、広く活用することができる概念です。
枝Dは、意図的に数的優位を作り出せる攻撃的なボールの奪い方のことで、自分の足元にボールを「残す」ことができます。
なぜ「残す」なのか ?もちろん答えは1つ。全ては得点(ゴール)のために─。
カテゴリ別新着記事
ニュース
-
 U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
-
 U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
フットボール最新ニュース
-
 近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
-
 「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
-
 【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
-
 リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
-
 前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
大会情報
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
お知らせ
ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |
人気記事ランキング
- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!
- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!
- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは
- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」
- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素
- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例
- 一生懸命走っているように見えない息子
- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」
- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること