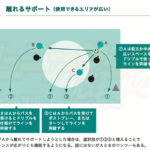「子どもの悩み」を解決! 親が気になるカラダのギモンQ&A②
2013年12月15日
コラム今回も「子ども」のカラダのギモンについて、2つ紹介します。ひとつは成長期で伸び悩むお子さんのお話と、食の細いお子さんについてのお悩みにアドバイザーが答えます。冬本番ののカラダづくりにご参考にしてみてください。
構成●戸塚美奈、編集部 写真●編集部
※『ジュニアサッカーを応援しよう!Vol.24冬号』P58-61より転載
Q.成長期に入って、子どもが伸び悩んでいる……。
20M先のゴミ箱にボールを投げるゲームで、10回のうち何回入るでしょうか。最初は1回も入らないかもしれませんが、1万回も練習すれば、8回や9回は入るかもしれません。その上達の過程をみると、成績がぐんと伸びた時期やあまり変化しなかった時期、時には成績が少し低下した時期があるはずです。こうした道筋を辿るのは自然なことです。
心理学では、ある技能レベル以上の場合で成績が停滞する時期を「プラトー」、熟達者に生じる成績の低下を「スランプ」、一定期間の休憩後に成績が向上することを「レミニッセンス」と言ったりします。また、サッカー協会は、思春期前後に生じるぎこちない動きのことを「クラムジー」と呼んでいます。
では、どうして順調に上達していかないのでしょうか。それは技能の複雑さ、練習方法、疲労の蓄積、やる気や集中力の低下など、様々な要因が原因となっていると考えられます。別の見方では、より上達するために、これまでとは違うやり方を学び直す必要があるとも考えられます。発達的にみると、背が高くなったり筋力が増えたりしますので、それに適した技能を習得するためとも言えます。
成長期の子どもの伸び悩みに対しては、まずは誰もが辿る道と考え、保護者としては「待つ」ことが必要です。子ども自身の気持ち、指導者の方針などで休まずに試合や練習を続けることもありますが、仮にオスグッド病などになっていた場合、悪化させてしまいます。子どもの成長には時間が必要なのですから、焦らずに休む・休ませる勇気が必要なのです。次に、リフレッシュできる環境あるいは練習内容を準備することが大切です。また、より知識の豊富な専門家にアドバイスを求めるのも良いかもしれません。いずれにしろ、子どもの場合は、楽しく練習できていれば、必ず上達していくものです。

アドバイザー
奥田援史先生
滋賀大学教育学部准教授。運動心理学が専門で、双生児研究や早期教育について調査をしている。サッカーは、小学1年から始め、関西高校ユース代表になったことがある。スポーツ少年団のコーチもしたことがある。現在、滋賀大学教育学部サッカー部監督。
カテゴリ別新着記事
ニュース
-
 【AFC U17女子アジアカップ インドネシア2024】U-17日本女子代表メンバー発表!2024.04.15
【AFC U17女子アジアカップ インドネシア2024】U-17日本女子代表メンバー発表!2024.04.15
-
 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!2024.04.11
「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!2024.04.11
-
 「東北トレセンU-13」が開催!2024.04.10
「東北トレセンU-13」が開催!2024.04.10
-
 【AFC U23アジアカップ カタール2024】U-23日本代表メンバー発表!2024.04.08
【AFC U23アジアカップ カタール2024】U-23日本代表メンバー発表!2024.04.08
フットボール最新ニュース
-
 近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.22
近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.22
-
 「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.22
「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.22
-
 【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.22
【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.22
-
 リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.22
リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.22
-
 前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.22
前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.22
大会情報
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
お知らせ
ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |
人気記事ランキング
- フォームの意識だけではキックは改善しない。キックの名手たちの共通点とは【フィジカルのプレーモデル】
- 自分よりも大きくて速い選手も1対1で抑える。内田篤人から学びたい守備時の姿勢【フィジカルのプレーモデル】
- 「もも上げクランチ」でキック力を鍛える!/【サッカー専用】小学生のための体幹トレ
- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- 三笘薫のドリブル・カットインの秘訣に迫る。1対1で相手を抜き去るための“沈む動き”とは【フィジカルのプレーモデル】
- 「2023ナショナルトレセンU-13 関東」参加メンバー発表!
- 4ゴールのゲームは守備の練習にはならない!? 課題となるタスクから逆算し正しく制約を課す【スモールサイドゲーム】
- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例
- 「2023ナショナルトレセンU-14 (後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- 「2023ナショナルトレセンU-14(後期) 」参加メンバー発表!【西日本】