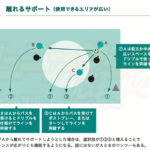なぜ今「認知」なのか。サッカーの戦術的な理解を広く深めることの意義【6・7月特集】
2018年06月29日
未分類6・7月は「認知」をテーマに特集を組んでいるが、アカデミックなテーマを取り上げているサッカー媒体は少ない。そんな中、ヨーロッパサッカー情報を発信し続けている「月刊footballista」は積極的に最新のサッカー戦術などの特集を組んでいる。そこで、編集長の浅野賀一氏にその理由と、また今回の特集テーマである「認知」についてどう考えているのかをうかがった。
【後編】サッカーの解釈を深く掘り下げる。認知とプレーモデルの関係
■第1回
状況判断の向上に「認知力」は必要不可欠である。その真意を説く
■第2回
「問いかける」だけではない。プレーの”選択肢”を広げるために指導者ができること
取材・文●木之下潤 写真●ジュニサカ編集部、佐藤博之
認知の捉え方には、身体的機能向上と戦術的理解向上の2つがある!
――月刊footballista54号の特集「欧州の新スタンダードを学べる 戦術用語講座」で「認知」を取り上げていました。ここ数年、最新のヨーロッパにおけるサッカー戦術などアカデミックな観点で媒体づくりを行われています。そもそもなぜ認知をキーワードに挙げたのか? そのあたりの理由から教えてください。
浅野編集長「2014年のワールドカップ・ブラジル大会から今回のロシア大会までが顕著なのですが、ものすごいスピードでサッカーが進化しています。ハーフスペースとか、5レーン理論とか、サッカーの新しい解釈が増えてきました。これらは発明ではなく解釈の仕方だと思うのですが、どんどん指導現場に取り入れられています。
これまで言語化されてない中でなんとなく指導されていたものがどんどん言語化され、それによりプレーの共通理解が広く深まってきました。それでサッカー界全体のレベルが上がり、ここ3・4年はすごい勢いです。そんな中でサッカーを言語化して語れる国内外の若い才能が現れてきて、footballistaの紙面にも登場してもらっています。彼らはみんな非常に優秀です。ものすごく勉強をしていますし、同じ人物に話を伺ってもたった1・2年しか経っていないのに話す内容が変わっていたり進化していたり。『どうして?』と質問すると、きっちりと理論的かつアカデミックな答えが返ってきます。そのベースには、サッカーの分析に必要な現象に対する解釈が不可欠です。彼らはそのベースを持っている。現象に対する解釈があるからサッカーの急激な進化が世界的に共有化されていき、ヨーロッパでは全体的に底上げが図られています。
そこで、みんな何となくは知ってはいるけど、でもきっちりとは掘り下げられていない戦術の新しい用語を一度ちゃんとフォーカスして特集してみたいなという意図で、54号の特集『欧州の新スタンダードを学べる 戦術用語講座』を組みました。ポジショナルプレーやハーフスペースなど『実際は何なの?』と言うところを具体的には答えられないから。
その中で、ヨーロッパサッカーの中でも頻繁に使われている『認知』という言葉は絶対に取り上げたいと考えました。私も何となくは知っていたのですが、 あらためて思うのは、 サッカーをプレーする上でも分析する上でも『認知』はベースとなるものだと思うのです。ドイツ在住指導者の中野吉之伴さんにも原稿を書いてもらいましたが、特にドイツは認知に関する考え方が進んでいるんです。
認知には2通りの考え方があり、その一つが認知する機能自体を鍛えること。それこそライフキネティックだとか、新しいテクノロジーを使ったフットボーナウトだとか、『目から脳、そして体への伝達機能を総合的に鍛える』アプローチです 。ライフキネティックは、お手玉をやりながらリフティングをしたり、ようするに『デュアルタスク』と呼ばれる2つ以上のものを同時に行動に起こすことで脳を鍛えていく。そういうサッカーから多少切り離された中で身体的な機能を鍛えていくやり方です。
≪フットボーナウト≫
それともう一つの方向性が、戦術的な方向性です。
認知を説明する時によく言われるのが、ピッチ上で経験する多くの状況をすでに知っている『既知』の状況にすると判断を自動化できるということ。既に知っていれば考えなくてもプレーできるようになるので、そのために戦術的なトレーニングでそういう状況をたくさん経験するようにしましょう、と。
認知には『機能そのものを鍛える方向』と『戦術的なトレーニングの方向』と2つの方向性があると考えています。目であったり脳であったりという部分は後天的に鍛えられるところもあるでしょうが、個人的には先天的な要素が大きいのではないかと思います。昨今、ヨーロッパサッカー界で重視されているのは後者、つまり戦術的なトレーニングで解決することです」
――私はライフキネティックのパーソナルトレーナーの資格を持っています。育成年代を中心に取材活動をしていて思うのは、サッカーで生かせるスキルそのものは後天的に伸ばせるものはあるけど、様々な機能の発達時期に合わせて鍛えた方がいいものがたくさんあり、より年齢が幼い頃に取り組んだ方がいいことがあります。認知を身体的な機能としての捉え方をすると、まさにそういう部分だと感じていたので取材する上での研究材料として資格を取得しました。
浅野編集長「サッカーは体を使うので機能という面は逃れられないもので、かつサッカーを解釈するという知識においても増やさなければならないものです。プレーの向上は、そういう両面のつながりを理解した上でトレーニングしなければならない。 それがプレーの質を高めることだと思うんです」
――しかし、日本サッカーでは一方だけで語ろうとして、本当は両方が必要なのに乖離して語られる傾向があります。解釈する側もそういう理解が足らなかったり、逆に語る側も知識が浅かったり。書く側の問題もあるのですが、結果それを情報として発信した時に機能と戦術がつながらなかったり、また技術と戦術がつながらなかったり。 そういう中で、世界では認知という部分が戦術的にトレーニングをする中で既知を増やしていく方向に進んでいて、それが一般化されています。だから、日本にもそういう考えが必要なんじゃないかと。

【footballista編集長の浅野賀一氏】
カテゴリ別新着記事
ニュース
-
 U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20
-
 U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13
-
 「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11
フットボール最新ニュース
-
 近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24
-
 「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24
-
 【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24
-
 リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24
-
 前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24
大会情報
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10
-
 【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09
-
 【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09
お知らせ
ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |
人気記事ランキング
- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】
- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!
- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!
- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは
- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」
- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素
- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例
- 一生懸命走っているように見えない息子
- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」
- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること